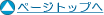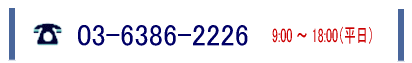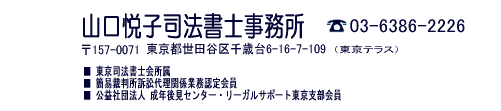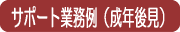

1.認知症の親の財産管理のため、施設入所のため、後見の申立をしたい
銀行等金融機関との取引や施設入所契約を行う場合、ご本人が契約の主体になれるのかどうか、判断能力を問われることがあります。判断能力が衰えている場合は、後見開始の審判の申立をおこない、選任された後見人が本人に代わって契約等を行うことになります。

「後見開始の審判」は、ご本人(被後見人)の住所地の家庭裁判所に申立てますが、この時、成年後見人候補者(親族、弁護士、司法書士等)がいれば記載します。ただし、申立時に記載した成年後見人候補者が選任されない場合もあります。また、成年後見人が弁護士や司法書士の場合、その報酬は家庭裁判所が決め、ご本人(被後見人)の財産から支払われます。

申立に必要な主な書類は次のようになります。
・申立書
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・本人の住民票又は戸籍附票
・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票
・本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
・本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書−未登記の場合は固定資産評価証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類など)
 【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
| 役務提供内容 |
報酬 |
別にかかる費用 |
| ・後見開始/保佐開始/補助開始の申立 |
88,000円〜 |
・申立費用等(こちらをご覧ください) |
※ご相談から書類の記載、代理権/同意権、目録作成など申立に必要なすべての手続を含みます。


2.介護費用を捻出するため、認知症の親の自宅を売却したい
判断能力が衰え、後見相当に該当すると契約の当事者にはなれません。そこで、そのような場合は、

1.「後見開始の審判」の申立をおこない、後見人を選任してもらいます。
2.選任された後見人が居住用不動産の処分許可の申立を行います。

後見人が、被後見人の所有している自宅を売却する場合は、家庭裁判所の居住用不動産の処分許可が必要になります。この処分許可の申立には、自宅を売却しなければならない理由や、売却価格、売却先、売却価格が適正なのかどうか等が判断されます。ご本人にとって自宅は精神的な支えとなっていることも多く、その処分には相当の理由が求められます。単に介護施設等に入所していて、自宅に住んでいないからといって、売却することはできません。
 【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
| 役務提供内容 |
報酬 |
別にかかる実費 |
| ・居住用不動産の処分許可の相談と申請書作成 |
33,000円 |
・申立費用800円(収入印紙)
・家庭裁判所指定による郵便切手代 |

3.相続がおこって遺産分割協議をしたいが、相続人である親に認知症の疑いがある
遺産分割協議は、重要な財産に関わる話し合いです。したがって、判断能力が衰え、自分にとって利益かどうかの判断がつかないような場合は、ご本人を保護するために後見人がご本人に代わって遺産分割協議に参加します。そのため、まず、後見開始の申立をして、後見人を選任してもらいます。また、後見人と被後見人である親がともに相続人の場合は、後見人と被後見人の利益が相反するため、被後見人のために特別代理人を選任し、特別代理人が遺産分割協議に加わります。特別代理人の選任の申立には、遺産分割協議書案の添付が必要で、被後見人に不利益となるような分割案は認められません。
 【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
| 役務提供内容 |
報酬 |
別にかかる実費 |
| ・特別代理人選任申立書の作成 |
33,000円 |
・申立費用800円
・家庭裁判所指定による郵便切手代 |
※後見の申立については、「1.認知症の親の財産管理のため、施設入所のため、後見の申立をしたい」をご覧ください。


4.今は元気だが、身寄りがないので将来が不安である。任意後見のことを知りたい
任意後見契約は、将来、判断能力が衰えてきたときのために、前もって後見人を決めておくことができる契約です。 そして、ご本人の判断能力が衰えてきた時に、その契約に基づいて、前もって決めておいた後見人が就任します。手続としては、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任」の申立を行うことで、任意後見契約が発効します。任意後見監督人が選任されて、後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的な報告をすることにより、問題が発生することを防ぐ仕組みになっています。

したがって、ご本人の判断能力の衰えを判断し、後見を的確にスタートさせるためには、
1.普段からご本人の生活の様子や状況を把握することが必要になります → 継続的な見守り契約
2.判断能力ばかりでなく、ご本人が病気等のために財産管理ができなくなる場合もあります。

そのような時のために → 財産管理等委任契約

「継続的な見守り契約」及び「財産管理等委任契約」を任意後見契約と同時に結んでおくと万全でしょう。

つまり、判断能力があるときは、定期的な電話または訪問により、ご依頼人の生活を守り、身体の不調等により外出などがままならなくなり、財産管理を託したいときは、財産管理等委任契約に切り替え、最終的に判断能力が衰えてきたら、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てて、任意後見に移行します。併せて、死後の事務(葬儀、埋葬)についても契約しておけば、ご依頼人の意思を実現することができます。
 【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
【上記手続を当事務所で代行する場合の報酬および費用】
| 役務提供内容 |
報酬 |
| ・任意後見契約 |
詳細はこちらをご覧ください |